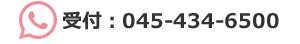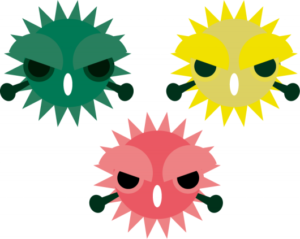
RSウィルスは、非常に感染力の強いウィルスで冬から春にかけて毎年流行します。風邪と似たような症状から始まって、鼻や咽頭の粘膜でウィルスが増殖し、主に呼吸器系のトラブルを起こします。特に呼吸器が未発達な乳幼児が感染すると、気管支炎や肺炎になって重症化する場合がありますので、早めの治療が大切です。
感染経路
RSウィルスは、くしゃみや咳で空気中に飛散したウィルスを吸い込んだり、鼻水やヨダレの付いたモノやオモチャを触った手で、目や鼻をこすったりして接触感染します。一度かかった事があっても何度でも感染する可能性があるので厄介です。2歳になるまでにほぼ100%の子どもが感染するといわれています。
主な症状
まずは鼻水から始まって、39度前後の発熱と咳が出ます。このウィルスに初めて感染する頃は、まだ2歳未満の乳幼児であることが多いため、未発達な気管が炎症を起こし、細気管支炎や気管支炎、肺炎へと進んでしまうケースが4割近くあります。「ゼーゼー」「ヒューヒュー」と呼吸する時に喘息のような雑音が聞こえて、喘息と勘違いする人がいますが、ほとんどの場合は8日~15日で回復します。
治療法
ウィルスというのは細菌と違って抗生剤は効きません。ですので、咳や鼻水、熱などの症状を緩和するお薬を使いながら、安静にして栄養をとって経過をみますが、乳幼児の場合は、病状が急変する可能性がありますので、呼吸が速く、浅くなってきたり、顔色が悪くなってきたら、迷わずにすぐに病院に行きましょう。
最近は、喉や鼻の粘液を調べれば、RSウィルスに感染したかどうかすぐに診断できるようになりましたので、ご心配な方はご相談下さい。
呼吸が苦しそうなときは、加湿器などで部屋の湿度を調節したり、呼吸が楽な姿勢で眠れるように工夫してあげましょう。
また、周りに感染しているお子さんがいる時は、おもちゃをミルトンなどの消毒液で拭いたり、手をこまめに洗ったりして予防しましょう。そして、睡眠と栄養を十分にとって、ウィルスに攻撃されてもそれをはねのける力(免疫力)を持つことが最も有効な対策になります。

【この記事を書いた人】医学博士 中野康伸
横浜市生まれ、自治医科大学卒
・日本小児科学会専門医
・日本アレルギー学会専門医
・日本東洋医学会専門医
横浜市港北区で小児科専門医として、地域に根差した診療を行っています。「病気・症状何でもQ&A」のコーナーでは、一般の方にも分かる最新の医学知識や予防接種の情報、育児・発育の心配な事、救急時の対応など、様々なトピックを掲載しています。