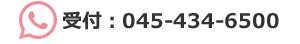何らかの原因(緊張、パニック、精神的不安など)で、呼吸が荒くなり、何度も吸って吐いてを繰り返すことで、過呼吸の状態になります。強い不安や緊張によって、自律神経や呼吸中枢に影響が出るために起こります。過呼吸状態になると、血中の二酸化炭素濃度が低くなるため、脳がこれ以上酸素は必要ないと判断することによって、酸素を吸うことができず、呼吸困難に陥ります。
血中の二酸化炭素濃度が低くなることによって、血液がアルカリ性になり、血管が収縮してテタニーと呼ばれる手足にしびれが出たり、けいれん、硬直、筋肉の収縮、さらには意識障害、失神が起きることがあります。こうした症状によって、さらに不安やパニックがひどくなり、呼吸状態はさらに悪化します。
子どもの場合は、家庭内の問題であったり、学校での人間関係などで強い不安や緊張を感じるケースが多いです。過度の運動による呼吸の乱れが誘因となる場合もあります。
対処法
ペーパーバッグ法といって、紙袋などを口に当てて、自分の吐いた息をもう一度吸うことで、血中の二酸化炭素濃度を上げる方法がありますが、あまり長く口に当てていると、逆に血中濃度が傾いてしまうので、ある程度落ち着くまでの短時間にしましょう。紙袋など適切なものがなければ、意識的に呼吸を止めて、体内の二酸化炭素濃度が上がるのを待ちます。その後は、ゆっくりとした腹式呼吸で呼吸するように促します。
またパニック障害の症状のひとつとして過換気の症状が出ることがあります。
ペーパーバッグ法でも落ち着かない、あるいはあまりに頻繁に過呼吸の状態になるような場合は、漢方薬や抗不安薬などを処方することもあります。重症な場合は心療内科などと連携をとって治療にあたります。

【この記事を書いた人】医学博士 中野康伸
横浜市生まれ、自治医科大学卒
・日本小児科学会専門医
・日本アレルギー学会専門医
・日本東洋医学会専門医
横浜市港北区で小児科専門医として、地域に根差した診療を行っています。「病気・症状何でもQ&A」のコーナーでは、一般の方にも分かる最新の医学知識や予防接種の情報、育児・発育の心配な事、救急時の対応など、様々なトピックを掲載しています。